通説編第4巻 第6編 戦後の函館の歩み
第2章 高度経済成長期の函館
第2節 地域振興と都市計画の推進
3 都市域の拡大と新たな地域課題
人口移動の実態と中心地の分散化
人口移動の実態と中心地の分散化 P358−P361
函館市の人口は、昭和60年以降急速に減少している。このことについて函館市は、その減少要因として(1)国鉄青函局の広域異動による転出、(2)函館ドックなど不況企業や倒産企業の離職者の転出、(3)土地価格が安い七飯、上磯など近郊の町に家を建てて転出することなどをあげている(昭和61年9月12日付け「道新」)。そして平成元年3月末現在、函館市の人口は31万人を割り、昭和51年の水準に戻った。函館市の人口は昭和40年代には横ばいを続けているが、市内の人口移動は急テンポで進んだ。とくに西部、中部、北部地域の人口が減った半面、新興住宅地の東部地域が急激に増え、なかでも日吉、花園地区は、同時期に約10倍もふくれあがっている。しかし、東部地区のこのような人口の伸びも、新興住宅地が公営住宅、個人住宅でいっぱいになってからは鈍化し、人口移動はまだ空き地の多い隣町の亀田町にはけ口を求めて流れることになった(昭和43年5月25日付け「道新」)。
 |
 |
人口の移動をさらに後押しした要因として、昭和48年の函館・亀田両市の合併がある。両市の境界線が消滅し、まるで堰を切ったかのように人口の旧亀田市への大移動が始まった。行政の境界線はそれまで、函館市民としてのこだわりが障害となって潜在的な壁の役割をはたしていたのかもしれない。合併後の数年間はちょうど核家族化とマイホームブームが同時に進行した時代でもあった(図2−13参照)。
このような人口移動は、昭和43年の新都市計画法の公布に伴う市街化区域の変更とも関係があろう。北海道が作成した函館圏の市街化区域の素案に含まれていなかった、函館市の榎本町、高丘町、上湯川町、根崎町、銭亀町などの各一部、亀田町の道道函館・上磯線(通称「産業道路」)の北側にあたる東山、神山、赤川通りなどが市民の要望により追加された(昭和45年11月28日付け「道新」)。産業道路は、昭和40年から工事が始まり、国道227号線まで4車線道路として53年9月12日に開通している(昭和53年9月10日付け「道新」)。函館市街地の拡大は、この2つの要因が重要で美原地区のような新たな商圏を形成する下地を作った(第7編コラム57参照)。
市街地の拡大は、その中心地の移動をもたらすことになる。具体的な事例として五稜郭、本町地区の歓楽街は昭和60年代に入って、目を見張るほどの成長ぶりで「やがて五稜郭全盛時代を迎える」との予測が強かった。直接の要因としてあげられるのは、昭和50年代に入ってから進んだ金融、損害保険関係など東京や札幌の大手出先の事業所が五稜郭周辺に立地したため、というのが定説であるが、函館ドックの合理化、北洋漁業の縮小、旧国鉄の人員整理など大門地区における顧客そのものの減少という事情も響いたことは否定できない(昭和62年5月17日付け「道新」)。
これらと関連して、函館市内の人の流れは函館駅前の大門方面から、五稜郭、本町などの五稜郭方面に移っている。とくに郊外の新興住宅地との往来が激しくなっていた。また、市内の移動手段別の割合は(1)自動車40.4パーセント(2)徒歩32.3パーセント(3)バスと市電12.5パーセントなどの順であり、旭川、札幌圏に比べ徒歩の割合が7ポイントから9ポイント高いのが特徴で、商店街が1か所に集中せず、函館駅前、五稜郭、美原方面などに分散していることが原因とみられた(昭和62年8月5日付け「道新」)。
この分散のありようを、昭和51年と60年の年間商品販売額から比較したのが次の数値である(図2-14参照)。函館駅前・大門地域が30.9パーセントから22.8パーセントに大幅ダウンし、本町・五稜郭地域は19.9パーセントから20.2パーセントに微増。これに対し、亀田商工会のおひざ元、美原・富岡地域は4.5パーセントから15.3パーセント近くもシェアが拡大した。この商圏の変化は昭和55年、大型小売店の長崎屋とイトーヨーカ堂が当地にあいついで進出したことが主因と考えられる(第7編コラム57参照)。このことが、函館の中心街はどこ、という疑問を生むことになった。
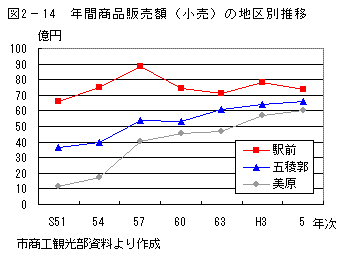 |
 整備が進んだ産業道路 |