通説編第4巻 第7編 市民生活の諸相(コラム)
第2章 復興から成長へ
コラム19
変わりゆくイカ漁
手釣りから機械釣りへ
コラム19
変わりゆくイカ漁 手釣りから機械釣りへ P693−P697
夏が近づくと街頭放送から「函館名物イカ踊り、イカ刺し・塩辛・イカソーメン、もひとつおまけにイカポッポ」、といった調子の歌が流れてくる。異国情緒あふれエキゾチックな街を観光のうたい文句にしている函館のイメージとは少しかけ離れた調子の歌ではないだろうか。「イカすまち函館」。これもまた函館観光のうたい文句のひとつである。イカは回遊魚で北は北海道、南は九州まで全国各地でさまざまなイカ漁がおこなわれている。それでも函館が「イカの街」と称されるのは、イカ漁が北洋漁業とともに函館水産業の中核をなしてきたからである(昭和31年1月1日付け「函新」)。再開された北洋漁業も昭和31(1956)年にはじまるソ連の規制措置や函館の基地としての地位低下によって年々かげりをみせていった(第6編第2章第3節参照)。その状況は、サケ・マスに袖にされた函館の生きる道はイカにた頼るしかないとも評された(同35年9月15日「道新」)。
イカ加工品の中心はなんといってもスルメであった。しかしこのスルメも時代の移り変わりとともにイカの燻製などの珍味にその座を明け渡していった。スルメの輸出が盛んだった昭和28、9年頃は漁獲高の80パーセントがスルメに加工されたが、同36年には30数パーセントに減少し、「イカくんが日の出の勢いで伸びてきたのは大衆の食生活にぴったりあったからだろうとビールがぐんぐん伸びるのに歩調を合わせ、そのつまみにイカくんがモテるわけ」と報道されるにいたった(昭和36年12月27日付け「道新」)。まさに日本が高度経済成長期に入り大衆の消費価値が変化し始め、食生活においてもその嗜好が多種多様化してきたことを示すものである。
ところで、函館のイカ漁を支えたのが各種のイカ釣り道具である。現在おこなわれているイカ漁は「全自動イカ釣機」「イカ釣ロボット」といった電動式のものが中心である。機械化が進む以前のイカ釣り道具はおもに佐渡から伝播したものといわれる(池田哲夫「佐渡式イカ釣具の伝播について(一)」『佐渡史学』第13集)。佐渡のイカ漁師は夏にイカを追って川崎船という船に乗って北海道に渡り漁をおこなっていた。
 昭和30年代なかばのイカ漁(「道新旧蔵写真」) |
 イカ釣りの道具を売る店(昭和39年、俵谷次男撮影) |
機械化以前のイカ漁は、水深50メートル以上の深いところにいる場合は「トンボ」、水深30メートル前後にいる場合は「ヤマデ」、水面付近にいる場合は「ハネゴ」といった道具を使用した。昭和27年の新聞記事によると「釣り具についても従来ハネゴには多くても針を四本しかつけなっかたものが、最近では十本から十五本もつける」ものがみられた(6月27日付け「道新」)。これらの道具の使用時期はだいたい昭和30年頃までであった。
なお、それ以降になると円筒形のドラムにテグスと針をつけた手回し式の手動イカ釣機が使用された。函館では「テマギ」と呼ばれた。住吉町辺りではドラムの両脇に仕掛けが付くことから「ダブル」とも呼ばれていた(住吉町在住イカ漁師談)。
その後自動イカ釣り機が開発されるが、函館においては、昭和31年から着手され、翌年には関鉄工所が「セキ式全自動いか釣機イカホーラー」を発売している。イカ漁の機械化が進むのは昭和30年代後半で、38年に大阪の鉄工所サンパーから発売された「全自動イカ釣機サンパー」が自動イカ釣り機の代名詞ともなり、昭和40年代には全国シェア90パーセント以上を占めた時期もあった(関鉄工所、サンパー鉄工所からの聞き取り)。
自動イカ釣り機の製作には北海道水産部の技術員が函館の業者などに働きかけたり、サンパーで開発された機械を導入するなどその普及に努めたりした。その後自動イカ釣り機を製作する企業は増え、ナショナルやヤンマーといったメーカーなども参画したがいずれも撤退した。現在日本で自動イカ釣り機を製造しているのは3社のみで、そのうちのひとつが「はまで式いか釣機」の商標で、昭和46年から自動イカ釣り機を販売している函館の東和電機製作所である(東和電機製作所からの聞き取り)。
自動イカ釣り機が普及する背景には労働力の軽減と発動機船の増加があった。昭和30年代に高度経済成長期をむかえ第1次産業の就業人口が減り、漁業に従事する後継者も減少した。自動イカ釣り機は、労働力を補う意味もあり急速に普及していった。大電力を必要とする自動イカ釣り機でも操業できるほどの発電機が、次々と開発されたこともその導入を助長した。古川町辺りでは「ハネゴ」や「トンボ」といった道具から、一足飛びに自動イカ釣り機に転換したそうである。
現在、自動イカ釣り機は長足の進歩をとげ、コンピューター制御により1人で30台を操作することが可能となっている。
さらに効率的な漁獲のために、集魚灯も進化した。昭和20年代後半から使われてきた白熱灯が、同50年頃からハロゲン灯やメタルハライド灯(放電灯)へと移行した。函館のイカ釣り漁船の場合は10トン級が主体で、ハロゲン灯(平均8個)と放電灯(平均36個)との併用船が多い(奈須敬二他編『イカ−その生物から消費まで−』)。
イカ釣り漁船がおりなす漁り火は、津軽海峡や函館山からの夜景に彩りを添える一方、現在では光量の増大競争が問題となっている。 (保科智治)
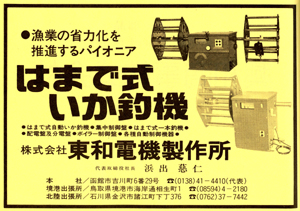 自動イカ釣り機の広告(1979年版『函館商工名鑑』より) |
 ドラム式の手動イカ釣り機 |
 自動イカ釣り機と集魚灯を装備した船(「道新旧蔵写真」) |